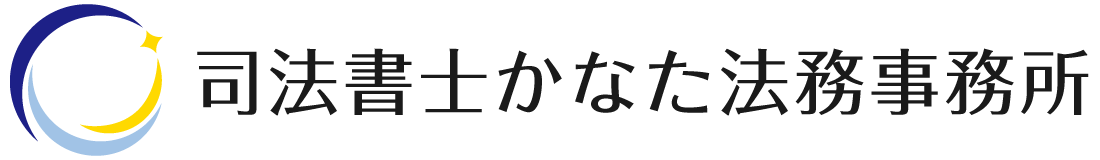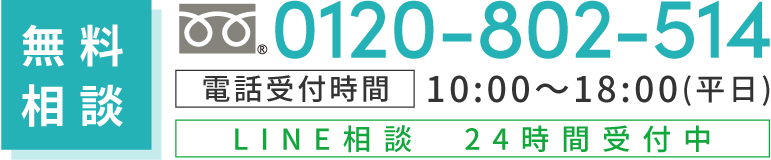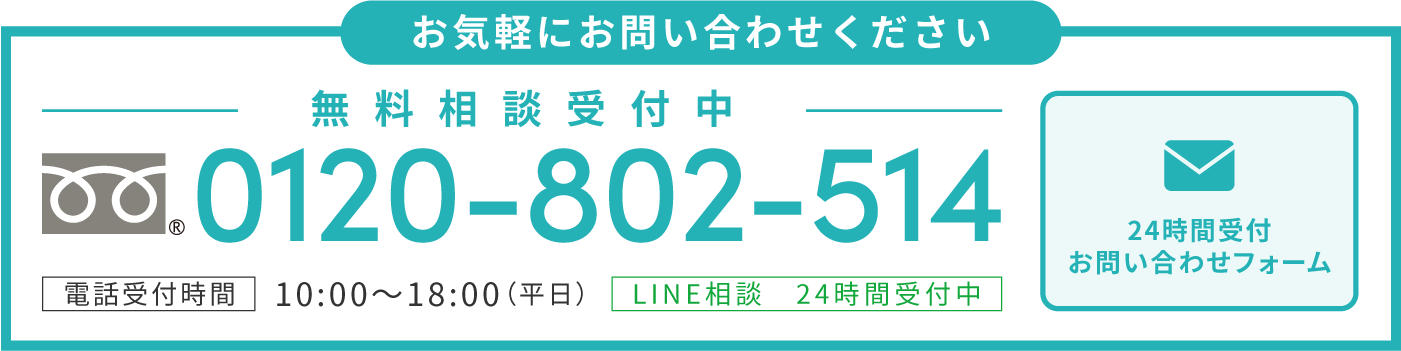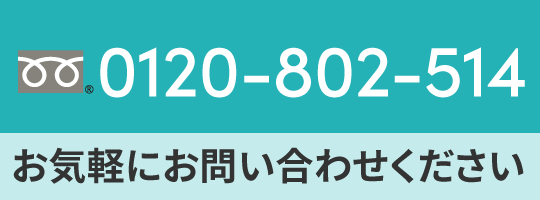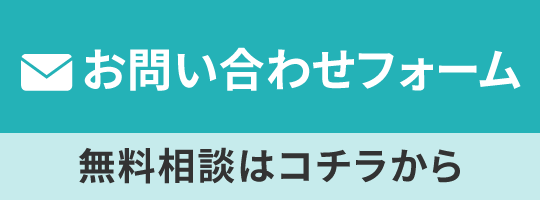相続にはさまざまなルールがあり、その中でも代襲相続は、特に理解が難しい制度の一つです。これは、本来相続するはずだった相続人が亡くなっている場合、その子(直系卑属)が代わりに相続するという仕組みです。
たとえば、被相続人(亡くなった方)の子が先に亡くなっている場合、孫が相続権を引き継ぐことになります。
本記事では、代襲相続の基本的な考え方、直系卑属による孫の相続のポイント、遺留分の注意点について詳しく解説します。
このページの目次
1. 代襲相続とは?
代襲相続とは、本来相続人になるべき人(子や兄弟姉妹など)が、相続が発生する前に亡くなっている場合に、その直系卑属(子や孫)が相続権を引き継ぐ制度です。
代襲相続が発生する主なケース
- 被相続人の子がすでに亡くなっている場合
→ 孫が代襲相続する - 被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合
→ 甥・姪が代襲相続する
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限り(甥・姪まで)で、孫やひ孫へは引き継がれません。
代襲相続が認められるための条件
- 代襲相続人(孫・甥・姪など)が、被相続人よりも先に亡くなった相続人の直系卑属であること
- 本来の相続人が、相続開始前に死亡していること(相続放棄や欠格・廃除の場合も代襲相続が発生)
2. 直系卑属による孫の相続の仕組み
被相続人の子がすでに亡くなっている場合、その子の子(孫)が相続権を持つことになります。
たとえば、次のような家族構成を考えてみましょう。
〈ケース1〉子が先に亡くなり、孫が相続する場合
家族関係
- 被相続人(祖父)
- 被相続人の子(父)→ 祖父より先に死亡
- 被相続人の孫(代襲相続人)
この場合、亡くなった父が相続するはずだった財産を孫が代襲相続することになります。
〈ケース2〉子が複数いる場合の相続割合
家族関係
- 被相続人(母)
- 長男(生存)
- 次男(母より先に死亡) → 次男の子(孫)がいる
この場合、相続分は以下のようになります。
| 相続人 | 相続割合 |
| 長男 | 1/2 |
| 孫(次男の代襲相続) | 1/2 |
孫が代襲相続する際、次男が持つはずだった相続分をそのまま受け継ぐのが原則です。
3. 代襲相続の際の遺留分の考え方
遺留分とは?
遺留分とは、被相続人が遺言で自由に分配できる財産の範囲を制限し、一定の相続人に最低限保障される取り分のことです。
例えば、父、母、子の3人家族で、父が母に「全財産を相続させる」との遺言を残したとしても、子は最低限の取り分を有する権利があります。これを遺留分と呼んでいます。
遺留分を請求できるのは、配偶者・子・直系尊属(親)に限られます。兄弟姉妹には遺留分がありません。
孫が代襲相続する場合の遺留分
孫が代襲相続人となった場合、遺留分の権利も引き継ぎます。
- 子が相続する場合の遺留分は法定相続分の1/2
- 孫が代襲相続する場合も同じ割合を受け継ぐ
たとえば、被相続人に妻と孫(代襲相続人)がいる場合、遺留分の計算は次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 妻 | 1/2 | 1/4 |
| 孫 | 1/2 | 1/4 |
孫も遺留分侵害額請求を行う権利があるため、遺言で「孫には一切相続させない」と書かれていても、最低限の取り分を請求できます。
4. 代襲相続での注意点
① 代襲相続は放棄できる?
可能です。孫が代襲相続人となった場合でも、相続放棄を選択することができます。ただし、相続放棄をすると、その財産は次の相続人(次順位の相続人)に移るため、事前に家族と相談して決めることが大切です。
② 代襲相続が発生すると手続きが複雑になる
代襲相続では、通常の相続手続きに加え、以下の書類が必要になります。
- 亡くなった父(または母)の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
- 孫の戸籍謄本(被相続人との関係を証明するため)
これらの書類を集めるのに時間がかかることがあるため、早めに手続きを進めることが重要です。
③ 相続税の計算も変わる
孫が代襲相続すると、通常の相続税に加え「2割加算」が適用される場合があります。ただし、孫が養子になっている場合はこの加算は適用されません。
5. まとめ
代襲相続は、相続人が先に亡くなっている場合に、その子(孫や甥・姪)が相続権を引き継ぐ制度です。
- 直系卑属(孫)による代襲相続は認められるが、兄弟姉妹の代襲は一代限り
- 孫が相続する場合も遺留分の権利を持つ
- 相続放棄も可能だが、慎重に判断する必要がある
- 手続きが複雑になりやすいため、早めの準備が重要
代襲相続は、通常の相続よりも手続きが煩雑になりやすいため、司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。