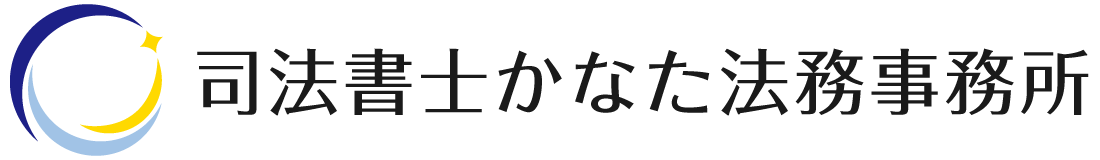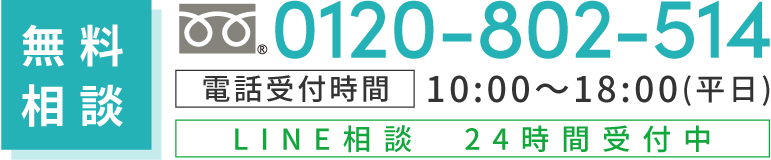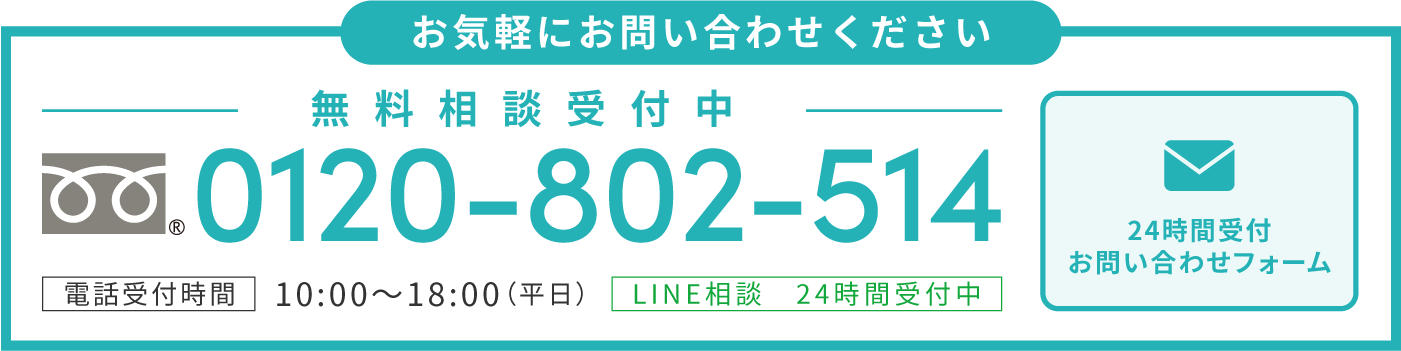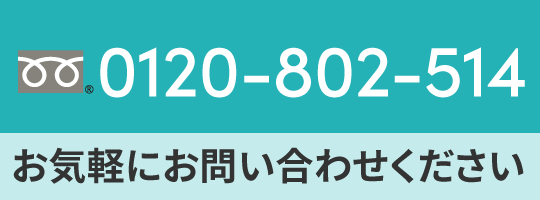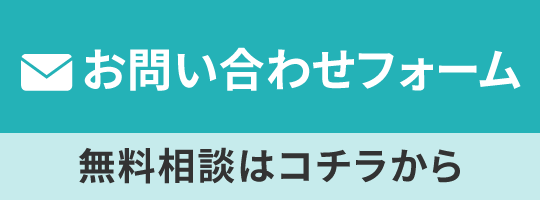不動産を相続した場合、不動産の名義変更(相続登記)を検討します。
これまでは相続した不動産の名義変更(相続登記)は義務ではなく、手続きをしないまま放置されるケースも少なくありませんでした。
しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化され、一定期間内に登記を行わなければ過料(一種の罰則)が科される可能性があります。
過去によく質問されることとして、「相続登記はいつまでにしなければいけないのですか?」というご質問があります。
今までは、「相続登記には期限はありません。また、登記しなければ罰則が科されるということもありません。」とお答えしていましたが、この回答が2024年4月1日から180度変わることになったのです。
本記事では、相続登記の義務化のポイント、不動産相続の流れ、登記手続きの方法について詳しく解説します。
このページの目次
1. 相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。
相続登記をしないとどうなる?
- 不動産の名義が亡くなった方のままになる
- 相続人が増え続け、権利関係が複雑化する
- 売却や担保設定ができなくなる
このような問題を解消するために、2024年の法改正で相続登記が義務化されました。
2. 相続登記の義務化とは?
2024年4月1日から相続登記が義務に!
これまで相続登記は義務ではなく、登記されない土地が増えることで所有者不明土地が全国で問題となっていました。所有者が不明な土地の総面積は九州と同じ広さということがニュースでも話題になっており、社会問題となっていたため、相続登記の義務化が決まりました。
義務化の内容
- 相続登記は、相続を知った日から3年以内に完了しなければならない
- 正当な理由なく登記しない場合、10万円以下の過料(一種の罰則)が科される可能性がある
過去の相続も遡って義務化の対象
この義務化は過去の相続についても一律に対象となりました。2024年4月1日以前の過去の相続については2027年3月末まで猶予期間があります。
相続登記未了の不動産はこれを機に早目に行動することが必要です。
3. 相続登記の流れ
相続登記を行うためには、以下の手順で手続きを進めます。
① 相続人を確定する
法定相続人を確認するために、被相続人の戸籍謄本を収集し、相続関係を明確にします。

② 被相続人の不動産を調査する
まず、亡くなった方が所有していた不動産の所在地や登記情報を確認します。
- 登記事項証明書を取得(法務局で取得可能)
- 固定資産税納税通知書で不動産を確認

③ 遺言書の有無を確認する
- 遺言書がある場合 → 遺言書の内容に従って相続登記を進める
- 遺言書がない場合 → 相続人全員で遺産分割協議を行う

④ 遺産分割協議を行い、協議書を作成する
遺産の分配方法を相続人全員で話し合い、合意が取れたら「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・押印(実印)します。

⑤ 必要書類を準備し、管轄法務局へ登記申請を行う
相続登記の申請に必要となる原則的な書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票除票・戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 遺産分割協議書(協議を行った場合)
- 登録免許税(法務局に提出する印紙代)
- 登記申請書
準備ができたら、管轄の法務局に相続登記を申請します。
4. 相続登記の義務化による罰則を免れる方法
相続登記の義務化により相続開始を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科されることがあります。
しかし、相続人が多数存在し、相続人の調査に時間がかかる、また、遺産分割協議書が整わずに時間がかかるなど、やむを得ない事情があり、すぐに相続登記ができるケースばかりではありません。
そのような場合でも、一律に罰則を適用するのは不合理といえるでしょう。そのため、今回の義務化に合わせて新しく設けられたのが、「相続人申告登記制度」です。
相続人申告登記は、各相続人が単独で申告することができるため、遺産分割協議が整わずに他の相続人の協力が得られない場合であっても問題はありません。他の相続人の承諾や同意を得る必要もありません。
これは、「私は相続人です」と法務局に申告することで、義務を果たせる制度です。
相続登記の義務化で定められた期限を過ぎてしまう場合には、とりあえずこの、「相続人申告登記制度」を利用して、過料(罰則)を免れることが可能となります。
しかしながら、相続人申告登記は、一種の仮の登記にすぎません。そのため、本来の相続登記とは違って、不動産を売却など処分したり、担保に差し入れたりすることはできません。
5. 登記手続きを自分で行う?専門家に依頼する?
相続登記は自分で手続きをすることも可能ですが、専門知識が必要で、書類収集や申請が複雑です。
自分で手続きする場合
- 費用を抑えられる(登録免許税のみ)
- 役所や法務局への申請が必要
専門家(司法書士)に依頼する場合
- 手続きをスムーズに進められる
- 書類の不備がなく、確実に登記できる
- 費用は発生するが、トラブル回避が可能
時間や手間を考慮し、登記の専門家である司法書士に依頼するのも選択肢の一つです。
なお、司法書士・弁護士以外の者が報酬を得て登記申請することは法律で禁止されています。
6. まとめ|相続登記を早めに行い、トラブルを防ぐ
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した場合は3年以内に登記をしないと罰則の対象になる可能性があります。
- 相続登記の義務化により、手続きの遅延が許されなくなった
- 不動産相続の手続きは、相続人確定・登記申請の順で行う
- 「相続人申告登記」など簡易手続きも検討する
- 手続きが複雑な場合は、登記の専門家である司法書士に相談するのが安心
不動産相続をスムーズに進めるためにも、相続が発生したら早めに手続きを開始することが大切です。