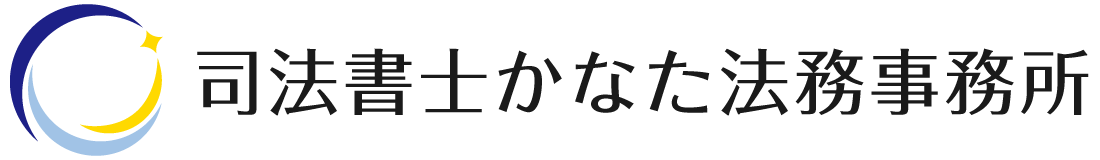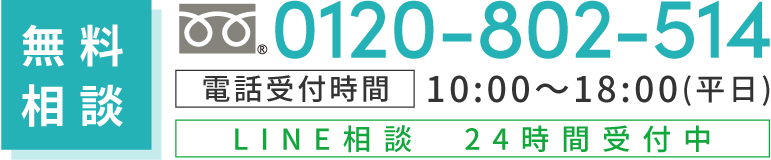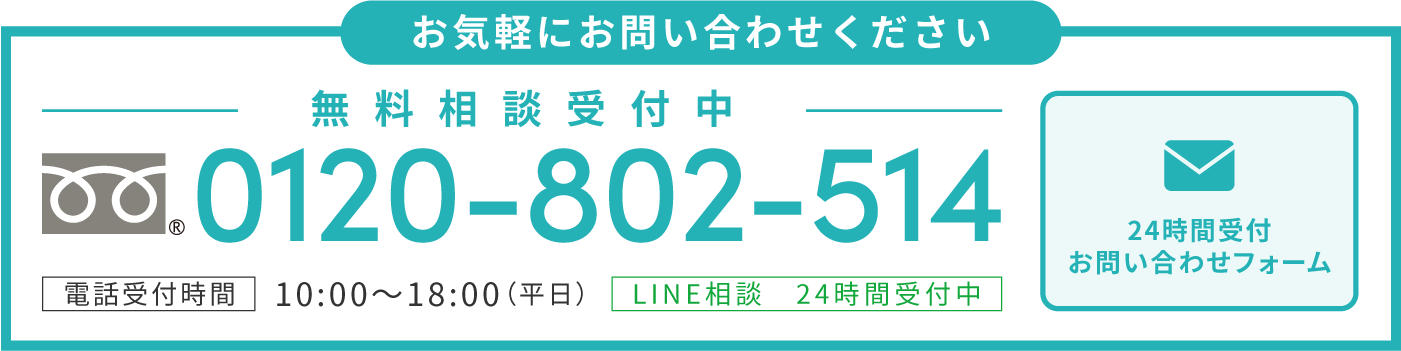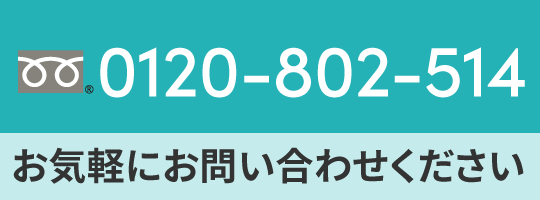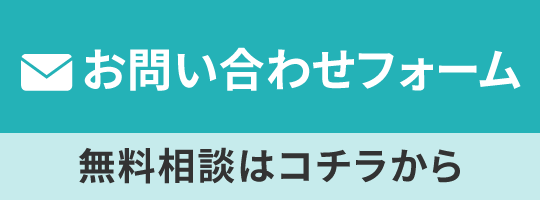不動産登記とは、土地や建物の権利関係を公に記録する制度です。これにより、不動産の所有者や抵当権の有無を明確にし、取引の安全性を確保できます。
不動産の取引や相続が発生した際には、適切な登記手続きを行う必要があります。特に、2024年4月から相続登記が義務化され、期限内に登記を行わないと過料(罰則)の対象となるため注意が必要です。
また、2026年4月から所有者の氏名・住所の変更登記が義務化も始まります。
本記事では、売買・贈与・財産分与・相続・抵当権設定・抹消に関する不動産登記の手続きやポイントについて詳しく解説します。
このページの目次
1. 不動産登記とは?
不動産登記は、土地や建物の権利関係を法務局に記録し、第三者に対して所有権や担保権を証明するための制度です。
不動産登記が必要となる主なケース
- 売買、贈与、財産分与による所有権移転(名義変更)
- 相続による不動産の名義変更(相続登記)
- 住宅ローンを利用する際の抵当権設定
- 住宅ローン完済時の抵当権抹消登記
正しく登記を行うことで、所有権を明確にし、不動産トラブルを防ぐことができます。
2. 当事務所に相談の多い登記と手続きの流れ
① 売買による所有権移転登記(名義変更)
不動産の売買をした場合には、必ず所有権移転登記をしましょう。所有権移転登記をせず、つまりは名義変更をしないと、他人に対して「この不動産は自分が所有者である」ということを主張することができません。
手続きの流れ
- 売買契約の締結
- 売主・買主双方で登記手続きの準備
- 必要書類の準備(権利証・印鑑証明書・売買契約書など)
- 司法書士が法務局に登記申請
- 登記完了後、新しい登記識別情報(権利証)と登記事項証明書を取得
注意点
- 登記をしないと、第三者に対して所有権を主張できない
- 登記費用(登録免許税など)が発生するため、事前に確認が必要
② 贈与による所有権移転登記(名義変更)
生前のうちに自分の不動産を子供(孫)に贈与したい、夫が妻に自分の不動産を贈与したいという相談が近年増えてきています。
不動産を贈与した場合には、登記をして名義変更をしておくことが大切です。贈与を受けた者が自分の所有権を他人に主張できるようにきちんと手続をしましょう。
手続きの流れ
- 贈与契約の締結
- 贈与者・受遺者双方で登記手続きの準備
- 必要書類の準備(権利証・印鑑証明書・贈与契約書など)
- 司法書士が法務局に登記申請
- 登記完了後、新しい登記識別情報(権利証)と登記事項証明書を取得
注意点
- 登記をしないと、第三者に対して所有権を主張できない
- 登記費用(登録免許税など)が発生するため、事前に確認が必要
③ 財産分与による所有権移転登記(名義変更)
離婚による財産分与として不動産を受けとった場合には、早目に名義を変更する登記をしておくことをお勧めします。
登記手続をしない間は自分がその不動産の所有者であることを主張できませんし、登記手続をしない間に相手の気が変わると、裁判所に訴えて不動産の名義を変更しなければならないという手間が生じる可能性もあります。
手続きの流れ
- 離婚協議書・財産分与協議書の作成
- 夫・妻の双方で登記手続きの準備
- 必要書類の準備(権利証・印鑑証明書・財産分与協議書など)
- 司法書士が法務局に登記申請
- 登記完了後、新しい登記識別情報(権利証)と登記事項証明書を取得
ただし、離婚が調停や審判で決まった場合には、相手方の協力なくして登記ができますが、必要書類がいろいろと変わってくるため注意が必要です。
注意点
- 登記をしないと、第三者に対して所有権を主張できない
- 登記費用(登録免許税など)が発生するため、事前に確認が必要
- 財産分与が、離婚調停や審判など、裁判手続きできまった場合には、相手方の協力なしに、単独で所有権を移転できる
④ 相続登記(名義変更)|2024年4月から義務化!
2024年4月1日から、相続登記の義務化がスタートしました。相続によって不動産を取得した場合、相続登記を行い、不動産の名義を変更する必要があります。また、この義務化は、2024年4月1日以前の相続にも適用され、過去に相続があった方でも登記を申請しなければ、過料(罰則)の対象になってしまいます。
相続登記義務化のポイント
- 相続を知った日から3年以内に登記を行う義務がある
- 2024年4月以前の過去の相続も義務化の対象となっている点に注意
- 期限を過ぎると10万円以下の過料(罰則)が科される可能性がある
- 相続人申告登記を利用すれば、最低限の手続きで義務を果たせる
相続登記の手続きの流れ
- 相続財産の調査(不動産の有無を確認)
- 相続人の確定(戸籍謄本を取得)
- 遺言書の有無を確認(遺言がない場合は遺産分割協議を実施)
- 遺産分割協議書の作成(相続人全員の同意が必要)
- 法務局へ登記申請
注意点
- 相続登記をしないと、不動産を売却できない
- 複数の相続人が共有名義にすると、後の売却や管理が難しくなる
- 過去の相続にも遡って義務化の対象となる
⑤ 抵当権設定登記(住宅ローン利用時)
住宅ローンを利用して不動産を購入する際、金融機関は不動産を担保として抵当権設定を行います。
抵当権設定登記の流れ
- 住宅ローンの契約締結
- 金融機関が抵当権の設定を決定
- 必要書類の準備(印鑑証明書・ローン契約書など)
- 司法書士が法務局に登記申請
- 登記完了後、登記事項証明書を取得して銀行に提出
注意点
- ローン完済後は、抵当権抹消登記を行わないと担保権が残る
⑥ 抵当権抹消登記(住宅ローン完済時)
住宅ローンを完済した場合でも抵当権の登記は勝手には消えません。銀行から発行される書類一式を基に、担保権の抹消登記を申請しなければいけません。
抵当権抹消登記の流れ
- 住宅ローンの完済
- 金融機関から抹消登記に必要な書類の交付がある
- 必要書類の準備(抵当権解除証書、銀行の権利証など)
- 司法書士が法務局に登記申請
- 登記完了後、銀行に報告
注意点
- ローンを完済しても、銀行が登記の抹消の手続きをおこなってくれるわけではない
- 抹消の手続きは自分でする必要がある
3. 不動産登記の必要書類と費用
不動産登記の主な必要書類
| 登記の種類 | 必要書類 |
| 所有権移転登記 (売買・贈与・財産分与) |
売買契約書、登記識別情報(登記済証)、印鑑証明書、固定資産評価証明書など |
| 相続登記 | 戸籍一式、住民票除票、相続人の住民票、遺産分割協議書、検認済遺言書、固定資産評価証明書など |
| 抵当権設定登記 | ローン契約書、登記識別情報(登記済証)、印鑑証明書など |
| 抵当権抹消登記 | 抵当権解除証書、金融機関の登記識別情報(登記済証)など |
登記にかかる費用
登記には、登録免許税(印紙代)や司法書士に依頼する場合には報酬が発生します。
登録免許税(税率の目安)
- 所有権移転登記(売買、贈与、財産分与):価格の2.0%(軽減措置あり)
- 相続登記:不動産価格の0.4%
- 抵当権設定登記:ローン借入額の0.4%
- 抵当権抹消登記:不動産1個につき1,000円
実際には、特例で軽減税率が定められており、司法書士は、軽減措置適用となるかを判断し税金の計算を行います。
ご自身で対応する場合には、仮に軽減措置を用いずに多く免許税を納付してしまっても、後に還付はできないため、気をつけないと損をすることになります。
4. まとめ|司法書士に依頼するメリット
不動産登記は自分の大切な財産をきちんと守るためのとても大切な手続になります。
しかし、登記申請は様々な添付書類が必要となる他、一言一句間違わないように申請しなければ登記が通らない等、一般の方にとっては馴染みがなく非常に分かりづらい手続でもあります。
司法書士は国が唯一認めている不動産登記の専門家です。当事務所では約10年近く登記業務に携わっている司法書士が担当しますので安心してお任せいただけると思います。
迅速に正確な登記を完了することをお約束します。登記のことでお困りのことがありましたら、是非ご相談ください。