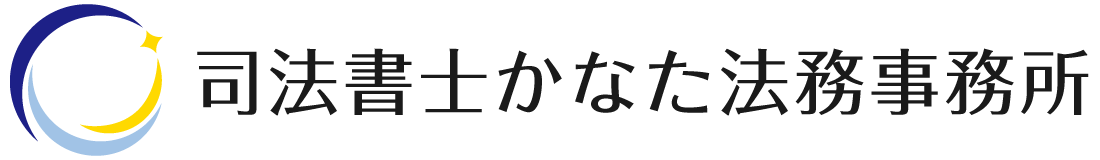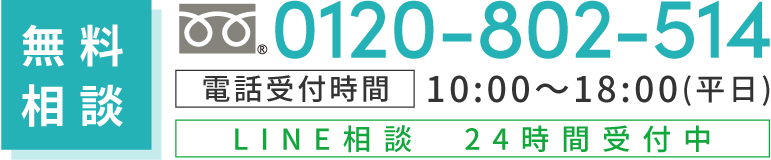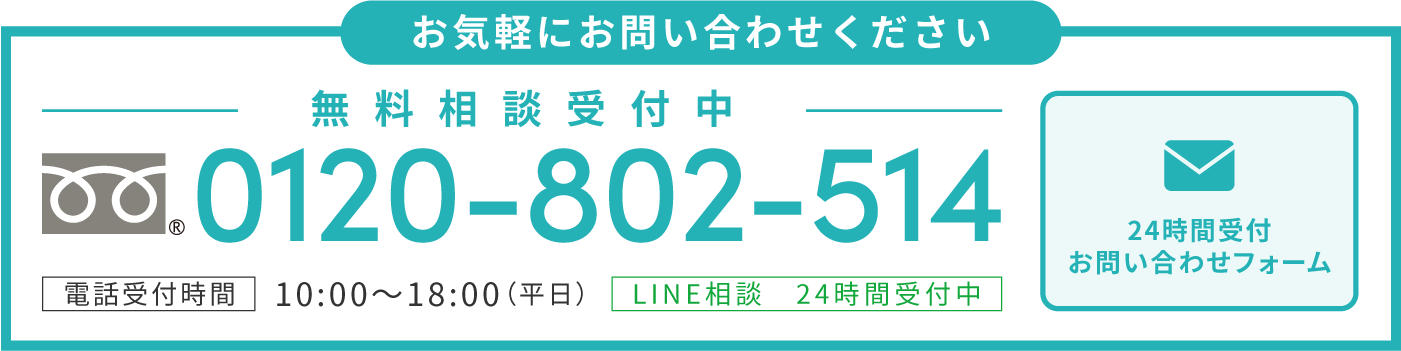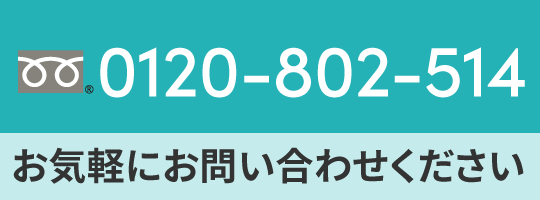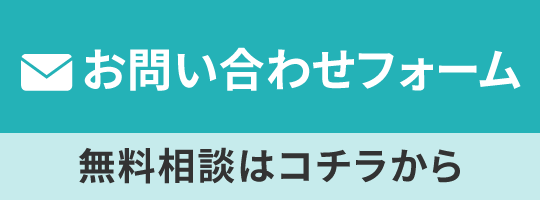家族や親族が亡くなった際、相続財産をどのように分けるかを決めるのが「遺産分割」です。遺産分割協議とは、遺言がない場合に、相続人全員が話し合い、遺産の分配方法を決定する重要な手続きです。
しかし、相続人の権利や法律上のルールを理解せずに進めると、遺産分割トラブルが発生することも少なくありません。特に「遺留分」や「特別受益」といった概念を知らずに協議を進めると、後々紛争に発展する可能性があります。
本記事では、遺産分割の基本的な流れ、協議の際の注意点、トラブルを防ぐ方法について詳しく解説します。
このページの目次
1. 遺産分割とは?
遺産分割の基本
遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)の相続財産を、相続人同士で話し合って分配する手続きです。
遺産分割が必要になるのは、以下のようなケースです。
- 遺言書がない場合(法定相続人で協議する必要がある)
- 遺言書があっても特定の財産について明記されていない場合
- 相続人全員が納得する形で遺産を分けたい場合
遺産分割が完了することで、不動産や預貯金の名義変更などの手続きを正式に進めることができます。
2. 遺産分割協議の流れ
① 相続人の確定
まず、法定相続人を確定します。相続人の範囲は民法で決められており、戸籍謄本を取得して確認する必要があります。
| 順位 | 相続人の範囲 |
| 第1順位 | 配偶者+子(直系卑属) |
| 第2順位 | 配偶者+父母(直系尊属) |
| 第3順位 | 配偶者+兄弟姉妹 |
※ 配偶者は常に相続人となります。

② 相続財産の調査
次に、被相続人の相続財産の全容を把握することが重要です。財産には次のようなものが含まれます。
- プラスの財産:不動産、預貯金、株式、貴金属など
- マイナスの財産:借金、未払いの税金、ローンなど
これらを調査した上で、遺産分割協議書に記載していく必要があります。

③ 遺産分割協議の実施
相続人「全員」で遺産の分配について話し合います。
話し合いの結果は「遺産分割協議書」として書面に残し、全員の署名・押印(実印)を行います。

④ 各種名義変更手続きの実施
遺産分割協議が完了したら、その遺産分割協議書を添付して、不動産の相続登記(法務局)、預貯金の払い戻し(各金融機関)、株式の名義変更(各証券会社)などの手続きを進めます。
3. 遺産分割協議の注意点
① 相続人全員の参加を確認する
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。一部の相続人が抜けたまま協議を進めると、無効となります。
当事務所で過去受けた相談において、問題があった代表的なものとその解決策をご紹介します。
相続人の一人が音信不通だった
このままでは遺産分割は成立しません。そのため当事務所で戸籍や住民票などを取得して不明になっている相続人の所在を調査し連絡をとり、無事に遺産分割がまとまりました。
相続人の一人が未成年者(18歳未満)だった
例えば、父が死亡し、相続人が母と未成年者の子であるような場合です。未成年者であっても、相続財産を承継することができるため、遺産分割協議は未成年者も含めて全員の同意が必要です。しかし、法律上、未成年者は自分で法律行為が行えず、法律行為を行う時には法定代理人の同意が必要とされています。
通常は、親権者(母)が法定代理人になるのですが、相続の場面において、親権者(母)と子が相続人の場合は親権者が子の代理人として遺産分割協議をすることができません。なぜなら母が子の法定代理人として認められてしまうと、母は子の取得分を自分より少なくするなど利益が反するおそれがあるからです。
こういった場合には、子の利益を守るために、家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらう必要があります。当事務所で、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行い、無事に遺産分割協議が成立しました。
相続人の一人に高齢で認知症の方がいた
例えば、兄弟相続で、高齢の兄が亡くなり、その兄弟である姉と弟が相続人になるような場合、姉と弟もそれなりに高齢であるケースが多いと思います。中には、認知症となり特別養護老人ホームに入所中といったケースもあります。
認知症を患っていたとしても相続人には変わりなく、財産を承継することができます。
しかしながら、遺産分割協議に参加するためには、自由な意思で納得して遺産分割協議に参加できる能力は必須です。そのため、判断能力を欠いている相続人が遺産分割協議に署名をしても無効となります。
こういった場合に利用できる制度として「成年後見制度」があります。成年後見とは、精神上の障がい(認知症、精神障がい、知的障がい)などで判断能力が不十分になった人の社会生活を支援する人(後見人)を家庭裁判所で選任してもらう制度になります。
成年後見制度を利用することで、成年後見人(認知症の方に代わって法律行為を行う)が遺産分割協議に参加し、署名・押印をしていくことになります。
当事務所で、家庭裁判所に成年後見人選任審判の申立をおこない、無事に遺産分割協議が成立しました。
② 特別受益を考慮する
生前に被相続人から多額の贈与を受けていた相続人がいる場合、「特別受益」として相続財産に持ち戻して計算する必要があります。
特別受益の例
- 生前に不動産の贈与を受けていた
- 多額の結婚資金や学費の援助を受けていた
- 多額の事業の資金援助を受けていた
特別受益を考慮せずに遺産分割を行うと、他の相続人の取り分が不公平になるため、事前に確認が必要です。過去にあったことをどこまで遺産分割で調整するのかは難しいところになりますが、このあたりの話し合いが円滑に行えるかが一つのポイントとなります。
③ 遺産分割におけるトラブル
遺産分割協議がスムーズに進まない場合、以下のようなトラブルが発生することがあります。
よくある遺産分割トラブル
- 相続人の意見が対立し、話し合いが進まない
- 特別受益が考慮されていないため、不公平感が生じる
- 相続人の一人に未成年者がいる
- 相続人の一人に、認知症を発症している方がいる
- 相続人の一人が行方不明で、連絡が取れない
解決策
- 相続人全員で冷静に話し合い、妥協点を見つける
- 特別代理人の選任を検討する
- 成年後見制度の利用を検討する
- 専門家(司法書士・弁護士)に相談し、公平な分割案を作成する
- 家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる(話し合いがまとまらない場合)
4. 遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議の結果を正式な書類として残すために、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書に記載する内容
- 被相続人の氏名・死亡日
- 相続人全員の氏名・住所
- 相続財産の詳細と分配内容
- 各相続人の署名・押印(実印)
注意点
- 相続人全員が署名・押印しないと無効
- 実印を使用し、印鑑証明書を添付する
- 法務局や金融機関での手続きに必要なので、必要不可欠な情報を盛り込む必要がある
5. まとめ|遺産分割協議は慎重に進めることが重要
遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続人の権利を尊重し、公平な話し合いを行うことが大切です。
- 相続人全員が参加し、遺産分割協議を進める
- 遺留分や特別受益を考慮し、公平な分配を目指す
- 遺産分割トラブルを防ぐため、必要に応じて専門家に相談する
- 最終的に遺産分割協議書を作成し、正式な手続きを行う
相続問題は、家族間の関係に大きく影響を与えるため、冷静に話し合いを進めるとともに、不動産の名義変更、銀行預貯金の解約など、確実に遺産分けが実行できるような書面を作成する必要があります。
司法書士は相続手続きに熟知した専門家です。相続手続きは専門知識を持った司法書士にお任せください。