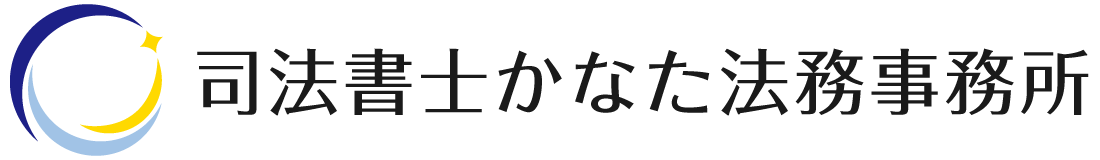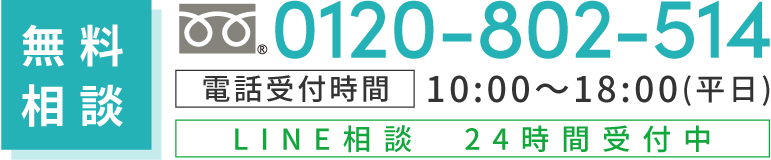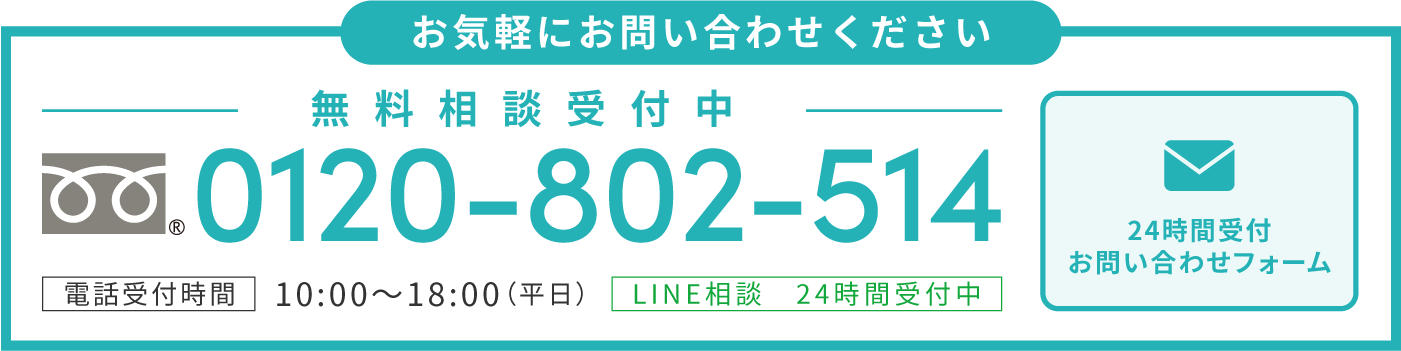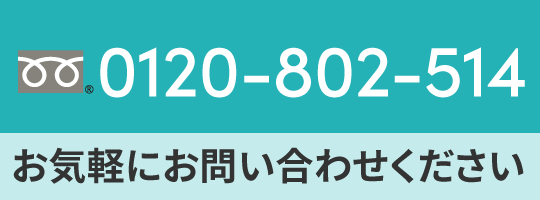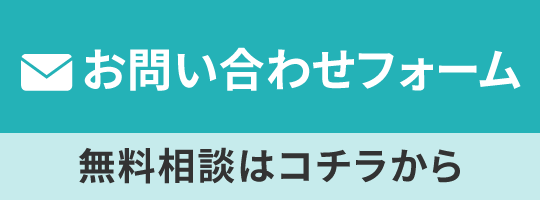家族や親族が亡くなった際、相続人はプラスの財産だけでなく、借金などの負債も引き継ぐ可能性があります。
もし、負債が多い場合、相続放棄や限定承認を検討する必要がありますが、これらの手続きには「熟慮期間」と呼ばれる期間制限が設けられています。
しかし、例えば、関係が疎遠になっている、一緒に暮らしていなかったというような状況によっては、負債があるのかないのかの調査が難しく、期限内に相続放棄をすべきか否かの判断ができない場合もあります。
そういった場合、家庭裁判所に熟慮期間の延長(期間延長)を申し立てることが可能です。本記事では、熟慮期間とは何か、延長のポイント、具体的な手続き、注意点について詳しく解説します。
このページの目次
1. 熟慮期間とは?
熟慮期間とは?
熟慮期間とは、相続放棄や限定承認をするかどうかを決めるための考慮期間です。民法では、「自己のために相続が発生したことを知った日」から「3ヶ月以内」に決定しなければならないと定められています。
つまり、相続人はこの3ヶ月以内に「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のいずれかを選択する必要があります。
熟慮期間の計算方法
自己のために相続が発生したことを知った日から起算
(通常は被相続人の死亡を知った日)
厳密にいうと、「相続が発生してから」3ヶ月以内にしなければいけないわけではありません。例えば、4月1日に死亡し、その死亡の事実を4月5日に知ったのであれば、4月5日から計算することになります。
もし3ヶ月を過ぎてしまうと、「相続を承認したもの」として単純承認(すべての財産と負債を引き継ぐ)とみなされるため、注意が必要です。
2. 熟慮期間の延長(期間延長)のポイント
期間延長を申請できるケース
相続財産の調査には時間がかかることが多いため、以下のような状況では家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることができます。
- 相続財産や借金の全容が把握できていない
- 遺言書や相続人の確認に時間がかかる
- 財産の資料収集に時間を要する(銀行や法務局の対応が遅いなど)
- 遠方に住んでおり、手続きを進めるのが困難
- 海外在住で対応が難しい
3. 熟慮期間延長の具体的な手続き
熟慮期間を延長するには、家庭裁判所に「相続放棄の熟慮期間延長の申立て」を行う必要があります。
正式なタイトルは、「家事審判申立書(相続の承認又は放棄の期間伸長)」となっています。
申立ての流れ
① 申立書を作成する
家庭裁判所に提出する「熟慮期間延長申立書」を作成します。
記載内容:
- 申立人の氏名・住所
- 被相続人の氏名・死亡日
- 相続を知った日
- 延長を求める理由(相続財産調査が困難な理由など)
- 希望する延長期間(通常1~3ヶ月程度)

② 必要書類を準備する
熟慮期間延長の申立てには、以下の書類が必要になります。
- 申立書(家庭裁判所指定の書式)
- 被相続人の死亡届の写しまたは戸籍謄本
- 申立人(相続人)の戸籍謄本
- 延長の必要性を証明する資料(財産調査に時間がかかる証拠など)

③ 家庭裁判所へ申立てを行う
書類がそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

④ 裁判所の審査を待つ
申立てが受理されると、裁判所が内容を審査し、妥当と判断されれば熟慮期間の延長が認められます。通常、1〜2週間ほどで結果が通知されます。
4. 熟慮期間延長の注意点
期間延長は「確実に認められるわけではない」
熟慮期間の延長は、裁判所の判断次第であり、理由が不十分だと却下されることもあります。そのため、延長を求める正当な理由と証拠をしっかり準備することが重要です。
申立ては「3ヶ月以内」に行う
熟慮期間延長の申立ては、元の熟慮期間(3ヶ月)内に行う必要があります。期限を過ぎると、相続を承認したとみなされるため、早めに手続きを進めることが大切です。
延長期間内でも相続放棄や限定承認の手続きを忘れずに
熟慮期間が延長されても、相続放棄や限定承認の手続きを先延ばしにしていると、最終的に単純承認となってしまう可能性があります。延長期間が終わる前に、必ず相続放棄や限定承認の手続きを進めましょう。
熟慮期間の伸長の申立ては、やむを得ない場合の手段です。そのため、相続放棄をするのであれば、なるべく元の期間内(3ヶ月以内)に準備をして、相続放棄の申立てをすべきといえます。
5. まとめ|熟慮期間延長を活用し、慎重に相続を判断
相続放棄や限定承認を検討する際、検討期間(3ヶ月)が足りない場合は家庭裁判所に期間延長を申請できることを理解しておきましょう。
- 熟慮期間は「相続開始を知った日から3ヶ月」
- 期間内に相続放棄や限定承認を決める必要がある
- 期限内に判断が難しい場合は「家庭裁判所に熟慮期間延長を申立て」
- 申立てには正当な理由が必要で、裁判所の判断によって延長が認められる
- 期間延長が認められても、相続放棄・限定承認の手続きを忘れずに行う
相続の手続きは時間がかかることが多いため、早めに準備を進め、必要に応じて熟慮期間の延長を活用することが大切です。
相続放棄の申立や熟慮期間の伸長の申立は、司法書士が資料を収集し、申立書などを作成することができますので、相申立て方法がわからない等の場合には司法書士に相談することをお勧めします。