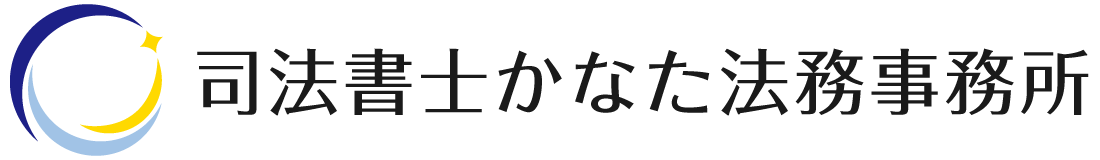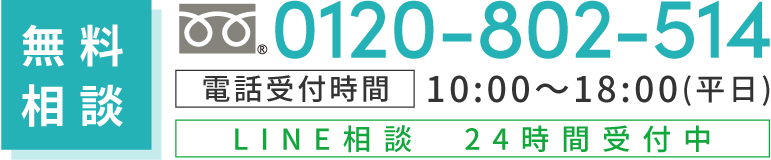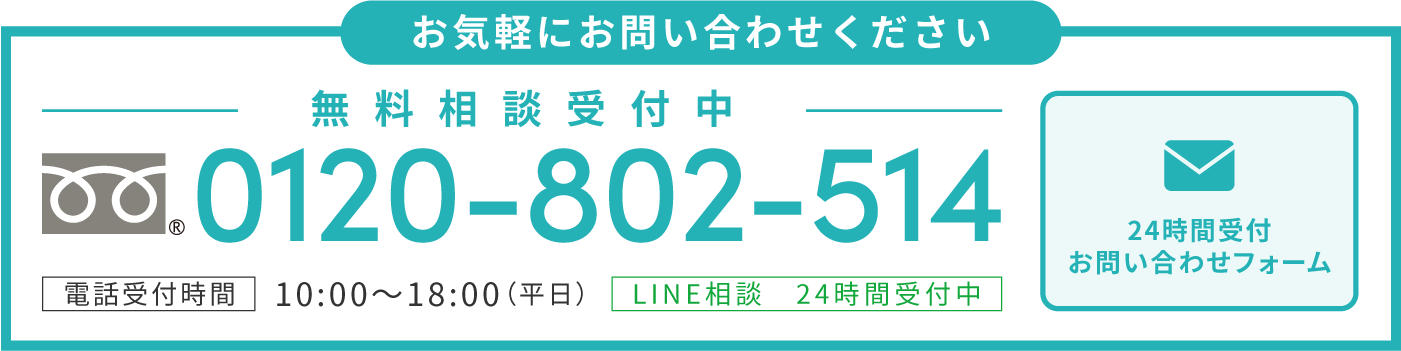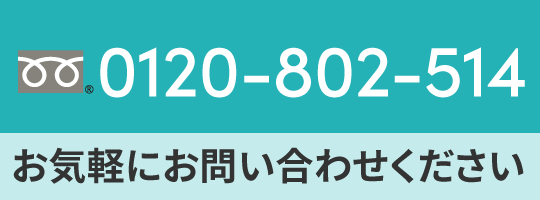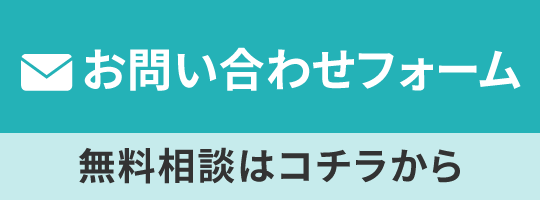このページの目次
1. 誰が相続人になるのか?(法定相続)
相続が発生し、被相続人(亡くなった方)が遺言書を作っていなかった場合、法律で定められた相続人へ、法律で決められた割合で相続されることになります。
これを法定相続といいます。法律(民法)に定められた相続人の順序と相続割合は、次のように決まっています。
① 相続人が配偶者と子の場合(第1順位の相続人)
- 配偶者 → 2分の1
- 子 → 2分の1
② 相続人が配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)の場合(第2順位の相続人)
- 配偶者 → 3分の2
- 直系尊属 → 3分の1
③ 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(第3順位の相続人)
- 配偶者 → 4分の3
- 兄弟姉妹 → 4分の1
つまり、配偶者は常に相続人となります。
また、直系尊属(祖父母等)は、子がいない場合に相続人となります。
そして、兄弟姉妹は、子と直系尊属(祖父母等)がいない場合にはじめて相続人としての地位を取得することになります。
2. 相続人を調べるためには
誰が相続人なのかを調べるためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を全て取得する必要があります。
相続人調査は相続において非常に重要なポイントとなります。
この相続人調査を怠ると、思わぬトラブルに発展することもあり、相続人が誰になるか予想ができる場合であっても、必ず戸籍を収集して相続人が誰であるかを客観的な資料をもって証明する必要があります。
さて、原則的に、戸籍は本籍地の市区町村役場で取得することができますが、ひとつの市区町村役場で出生までの戸籍が揃うことは稀です。過去に転籍をしていることも多く、何箇所も市役所を回って戸籍を集めなくてはならないことも珍しいことではありません。
戸籍を請求することができるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族であり、本籍地が遠方にある場合や仕事等の都合で平日休めない場合には郵送により取得することもできますが、この戸籍を集める作業は非常に手間を取られる作業のひとつです。
3. 戸籍の広域交付制度
ところが、2024年3月1日から戸籍の「広域交付制度」という制度が始まりました。
これは、最寄りの市役所、区役所において、全国どこに本籍があろうが、一括してその最寄りの役所のみで戸籍を収集できる制度です。
この制度によって、戸籍収集の作業はだいぶ楽になると思われます。しかし、この戸籍の広域交付制度にも弱点があります。
主な注意点は下記の3つです。
- 兄弟姉妹の戸籍は請求できない
- 郵送や第三者による請求はできない
- 戸籍の附票など、相続登記に必要な書類が漏れなく集められる訳ではない
① 兄弟姉妹の戸籍は請求できない
この制度を利用して集められる戸籍は、本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属に限られています。
したがって、兄弟姉妹やおじやおばなどの戸籍謄本を請求することはできないため、制度上まだまだ発展途上といえるでしょう。
② 郵送や第三者による請求はできない
戸籍は郵送でも請求したり、第三者に委任をして請求を依頼することができます。しかし、この広域交付制度の場合には、必ず「本人」が「窓口」に出向く必要があります。
したがって、仕事等の都合で多忙で平日休めない場合には利用が難しくなります。
③ 戸籍の附票など、相続登記に必要な書類が漏れなく集められる訳ではない
不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類は、単に「戸籍」のみならず、「住民票の除票」や「戸籍の附票」といった書類も必要となってきます。
しかし、そういった書類までこの広域交付制度は対象としていません。
結局は、従来別途本籍地を管轄する市区町村役場の窓口か郵送の方法で請求する必要があります。
4. 面倒な戸籍の収集の丸投げもOK
このように、戸籍の収集の作業は一般の方にとっては時間もかかりとても面倒な作業です。また、戸籍の広域交付制度によっても、完全に書類が収集できるわけではありません。
そして、何より、仮に戸籍が集まっても、その戸籍に書かれている内容を正確に把握し、相続人を確定する作業は一般の方には非常に難しい作業になります。
司法書士に依頼すれば、司法書士は職権で戸籍を取得することができますし、誰が相続人になるのかを正確に調査することができます。
その上で、法定相続に従った場合に相続分の割合は各人どうなるのかなどを調べることができるため、思い切って戸籍の収集を丸投げされる方が楽かもしれません。