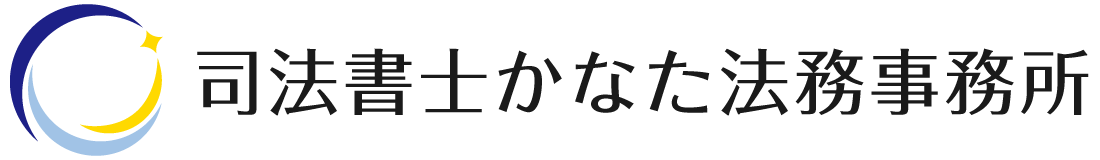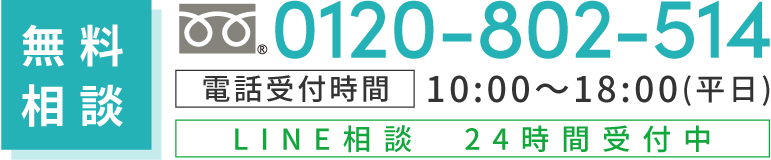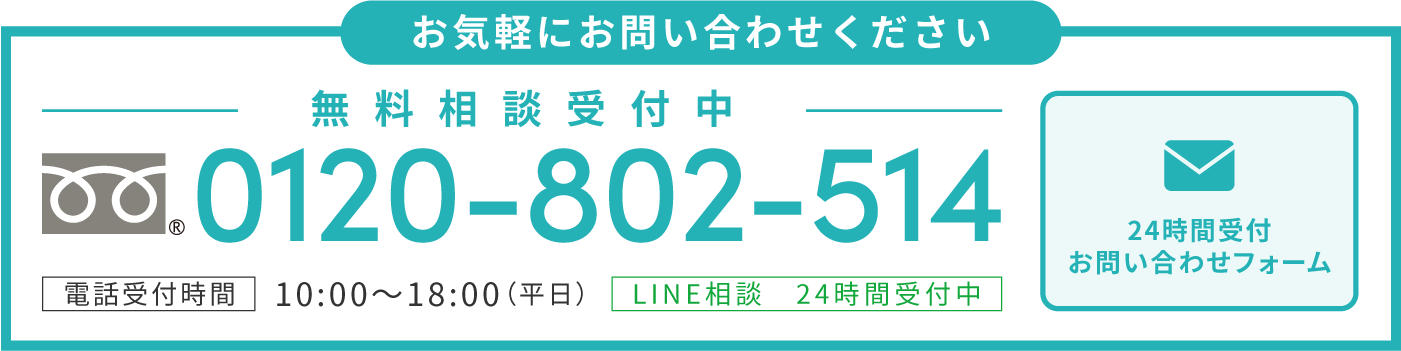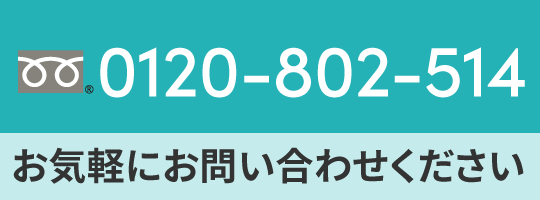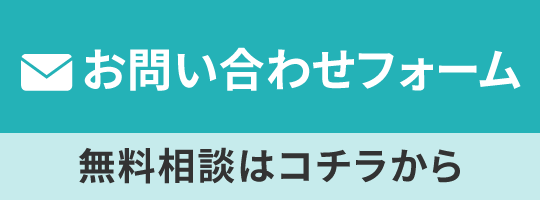登記業務とは、「不動産」や「会社」の権利関係を公に証明するための手続きのことを指します。
登記を適切に行うことで、不動産の所有者を明確にしたり、会社の情報を公的に管理したりすることが可能となり、我が国の重要な情報となっています。
近年、登記制度に関する法律が相次いで改正され、特に一般の市民とかかわることとして、2024年4月から「相続登記義務化」が施行されました。これにより、相続登記の手続きを放置すると過料(罰則)が科される可能性があり、より迅速な対応が求められるようになりました。
また、2026年(令和8年)4月から不動産の所有者について、「名前・住所の変更登記が義務化」されます。氏名・住所の変更があった場合には、変更があった日から2年以内に変更登記をすることが義務とされました。これも、相続登記義務化と同様に、変更登記を放置すると過料(罰則)が科される可能性がでてきます。
本記事では、登記業務の種類、不動産登記と商業登記の違い、登記手続きの流れ、相続登記義務化、氏名住所変更登記義務化のポイントについて詳しく解説します。
このページの目次
1. 登記業務とは?
登記業務とは、不動産や法人に関する権利関係を登記簿に記録し、公に証明する手続きのことです。登記を行うことで、第三者に対して自分の権利を主張でき、また、取引をする相手方は、登記記録(登記簿)を閲覧することによってトラブルを防ぐことができます。
主な登記業務の種類
- 不動産登記:土地や建物の所有権や抵当権などを記録する
- 商業登記:会社や法人の設立・役員の変更などを記録する
登記業務は、各管轄法務局で管理されており、誰でも理由なく、不動産登記記録(登記簿)、商業登記記録(登記簿)を取得することができます。
そのため、登記記録(登記簿)は正確であることが求められます。その、登記記録を書き換える業務が、登記業務といえます。
登記は当事者の申請によってされることになります。
2. 不動産登記とは?
不動産登記の目的
不動産登記とは、土地や建物の所有権や権利関係を公に証明するための制度です。
不動産の売買や相続が発生した際、適切に登記を行わないと、所有権を第三者に主張できず、権利トラブルに発展する可能性があります。
不動産登記の主な種類
| 登記の種類 | 概要 |
| 所有権保存登記 | 新築建物の最初の登記 |
| 所有権移転登記 | 売買・相続・贈与・財産分与などによる名義変更 |
| 抵当権設定登記 | 住宅ローンを組む際に金融機関が権利を設定 |
| 担保抹消登記 | 住宅ローン完済などによる抵当権抹消の登記 |
| 相続登記 | 相続による不動産の名義変更 |
3. 商業登記とは?
商業登記の目的
商業登記とは、株式会社や法人の基本情報を法務局に登録し、公的に証明するための制度です。
会社の設立や役員変更などを登記することで、第三者はどういった会社と取引を行うのかを事前に確認することができ、取引の安全性が保たれます。
商業登記の主な種類
| 登記の種類 | 概要 |
| 会社設立登記 | 株式会社や合同会社の設立時に行う登記 |
| 本店移転登記 | 会社の本店所在地を変更する場合に必要 |
| 役員変更登記 | 代表取締役や取締役の変更(就任・辞任・解任) |
| 増資・減資登記 | 資本金の増加・減少 |
商業登記は、会社の信頼性を維持するために重要な役割を果たしており、会社(法人)の登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条1項)。
2週間の期限を経過した後に登記申請すると、ペナルティーとして会社(法人)の代表者に対して過料(一種の罰金)の制裁を受ける可能性があります。会社の信用を落とさず、ペナルティーを防ぐ上でも、登記事項に変更が生じた場合には、早い段階で登記申請することをお勧めします。
4. 相続登記の義務化とは?(2024年4月施行)
相続登記義務化の背景
これまで相続登記は任意であり、相続人が登記を行わずに放置するケースが多く見られました。その結果、所有者不明の土地が増加し、行政や個人間でのトラブルが発生していることが社会問題となっていました。
そこで、この問題を解決するため、2024年4月1日から「相続登記の義務化」が施行されました。
相続登記義務化のポイント
- 相続登記は3年以内に行う必要がある
→ 相続を知った日から3年以内に登記をしなければならない - 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料(罰則)が科される可能性がある
- 「相続人申告登記」で簡易的な手続きも可能
→ 相続登記がすぐにできないような事情がある場合、 相続人であることを法務局に申告するだけで、過料を免れるなど、一定の義務を果たせる制度ももうけられた。
相続登記手続きの流れ
- 戸籍謄本・遺言書の確認
- 相続人全員で遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議書を作成
- 法務局へ相続登記を申請
5. 氏名・住所変更登記の義務化とは?(2026年4月施行)
氏名・住所登記義務化の背景
不動産の所有者の氏名や住所に変更があっても、これまでは、登記は任意でした。
しかしながら、相続のケースと同様に、登記を行わずに放置されることにより、所有者と連絡がつかないなどトラブルが生じ、その結果、所有者不明の土地が増加する原因の一因といわれていました。
そこで、この問題を解決するため、2026年4月1日から所有権登記名義人の「氏名・住所変更登記の義務化」が施行されることとなりました。
氏名・住所変更登記の義務化のポイント
- 変更登記は2年以内に行う必要がある
→ 変更日から2年以内に登記をしなければならない - 正当な理由なく放置すると5万円以下の過料(罰則)が科される可能性がある
- 「検索用情報の申出」をすることにより、職権で登記がされる
→検索用情報の申出という制度が、2025年4月21日から変更登記の義務化に先駆けてスタートしています。
事前に検索用情報の登録を申請(無料)することによって、氏名・住所に変更があった際には、法務局が職権でおこなってくれるという制度です。
具体的には、個人情報やメールアドレスなどの情報を法務局に届出て登録することにより、氏名・住所の変更があっても自ら登記を申請することがなくなります。
6. 登記手続きをスムーズに進めるためのポイント
- 必要書類を事前に確認し、不備のないよう準備する
- 期限内に登記手続きを行い、罰則を回避する
- 複雑なケースでは司法書士など専門家に相談する
登記手続きは、法律に基づいて適正に行う必要があり、不備があると受理されない等、他の行政手続きとは違った細かい手続きとなります。
7. まとめ|登記の重要性と司法書士に依頼するメリット
登記業務の重要性
- 不動産登記は、土地や建物の所有権を明確にし、権利トラブルを防ぐためにある
- 商業登記は、会社の情報を公にし、取引の安全性を確保するためにある
- 2024年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内の手続きが必須
- 2026年4月1日から氏名・住所の変更登記が義務化され、2年以内の手続きが必須
- どちらも義務を怠り、期限を過ぎると過料が科される可能性がある
司法書士に依頼するメリット
登記は実に身近なことに関わり、常に生じるものといえますが、なかなか一般の方にとっては馴染みのないものではないでしょうか。
最近では、確定申告などはわざわざ税理士さんに依頼せず、ご自身でパソコンを用いて申請する方も増えてきていますが、登記申請をご自身でやられる方は滅多におりません。
それは、登記申請には実に多くの添付書面が必要となり、書面に押す印鑑も、実印を要求される箇所や認印で足りる個所など、非常に細かく法律で規定されていており、一般の方が把握するのは困難といえるからです。
また、一言一句間違わずに申請しなければならず、たった一文字間違っただけでも訂正ができなかったり、登記申請自体が却下されてしまったりと、細かい作業が要求されるためご自身で申請するには相当な労力がかかってしまいます。
司法書士は、登記の専門家として国が唯一認めている国家資格です。
当事務所では、約10年近く登記業務に携わっている司法書士が担当しますので安心してお任せいただけると思います。