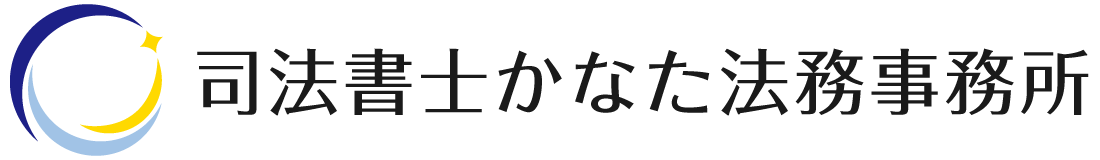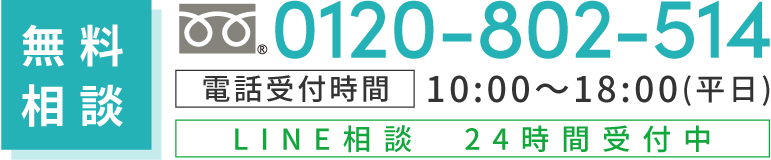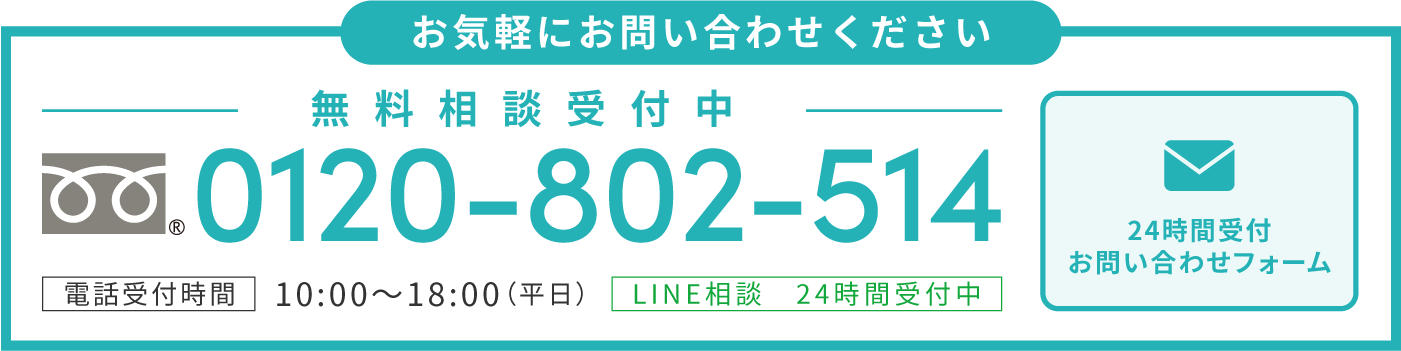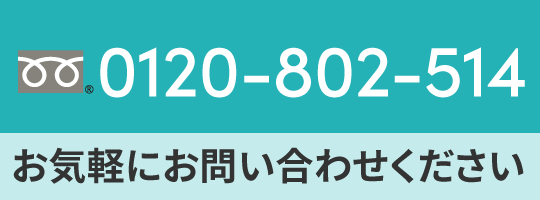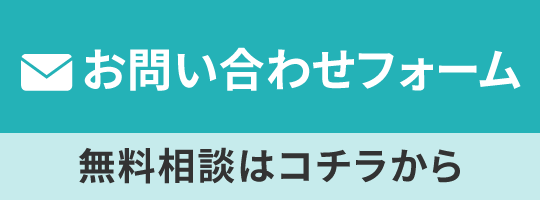このページの目次
1. もしかしたら夜逃げ??
意外と多い相談として「夜逃げ」のご相談があります。
家賃が支払わなくなりしばらく時間が経過した後に、全く音信不通になるパターンでは夜逃げの可能性もあります。
単なる居留守を使っているだけか、夜逃げかの区別はおおよそ以下の点をチェックすると判別できます。
チェックポイント3つ
- 郵便ポストに郵便が溜まりっぱなしになっている
- 夜になっても電気がついていない
- 水道ガスのメーターが止まっている
電気・ガス・水道は生活をしていれば絶対に利用するものであるため、ライフラインの利用状況はとても分かりやすい判断基準になります。
ポストについても、通常であれば帰宅時にポストを開けることが多いため、郵便が溜まりっぱなしの状態は異常といえるでしょう。
ただし、経験上、家賃滞納者の中には、実際に住んでいるにも関わらず、ポストを見ないといった方も多い印象があります。
ルーズな性格が現れているともいえますので、ポストのみで夜逃げと判断するのは早計です。必ずライフラインのチェックを合せてしてください。
2. 夜逃げの場合に絶対にやってはいけないこと
夜逃げと思われる際にも絶対にやってはいけないことはただ1つ、スペアキーにて居住スペースに立ち入り家具や残置物を勝手に撤去することです。
難しい用語で「自力救済の禁止」といわれるものですが、要するに、法の手続きに基づかずに私的に処理するのは禁止という意味合いです。
仮に、勝手に家具・家財を撤去処分すると・・・
- 居住スペースに勝手に立ち入ることは、住居侵入罪(刑法130条)として、3年以下の懲役刑・罰金刑の罪に問われる危険性があります。
- また、家具や家財道具を勝手に撤去したり処分したりすることは、不法行為として後に損害賠償責任を追及される恐れがあります。
明らかに夜逃げだろうと思われる場合には、賃借人が戻ってくる可能性が低いため、部屋の中の残置物を撤去処分し、鍵を交換して、早く賃貸に出したい気持ちは痛いほど分かります。
家主としては、家賃も払わず行方も知らない状態になったのに、罪に問われる可能性があるというのは、あまりに不合理だと感じるのは当然といえますが、この点はどうしても法律に基づいて手続きを取らざるを得ません。
3. 契約書に住居の立ち入りと家財道具の処分を定めたら有効?
仮に、事前に賃貸借契約書に「連絡が取れない期間が2ヶ月に及んだ場合には、残置物は賃貸人によって処分することができる」と事前に記載がある場合にも、ここにいう残置物とは、他人が見ても不要品と思われるような物品を指し、通常の家具、家電は含まれないと解されることから、このような事前の取り決め条項が無効となる可能性があります。
よって、賃貸借契約書に定めたからといって、住居への立ち入りや家財処分が有効になるわけではありません。
4. 夜逃げの場合の対処法
通常の家賃滞納と同様に、賃貸借契約の解除をし、明渡しの裁判で勝訴判決を取得し、強制執行にて残置物の処分をする必要があります。
夜逃げの可能性が高いケースでは、相手方が裁判に出頭し、異議を申立てるといったことはまず考えられません。
そのため、家主側の主張が認められて、勝訴判決まではスムーズに進むのが通常です。要するに結論は見えているため、あとはどれだけ早く手続きを終えられるかという点がポイントになります。
当事務所では、裁判所に状況説明をするなど出来るだけ時間が短縮できるように進めています。
5. 最近増えている相談(孤独死)
最近増えつつあるのは、実は孤独死です。現代の高齢化社会を反映している問題といえます。
ポストに郵便が溜まる、ライフラインが止まっているという「夜逃げ」と思われるような状況と共通する部分がありますが、違いは、賃借人が高齢者の一人暮らしという点です。
また、死後数週間が経つと、異臭が発生してくるため、同じ建物の住人から苦情が出て発覚することがあります。
異臭が発生している場合には、孤独死、事故死、事件等の可能性があるため、すぐに救急と警察に連絡すべきです。警察立会いの下、部屋の鍵を開け、あとは警察の判断を待つことになります。
事件性がないと確定された場合には、それ以上の処理は警察ではしてくれません。家主側で緊急連絡先、保証人、親族、相続人と連絡をとり、今後の処理を話し合う他ありません。
しかし、近時は、相続人であっても疎遠であることを理由に、相続放棄をされ、協力を得られない場合が増えています。
最終的には、相続人を探し、相続人がいない場合には、相続財産管理人を申立てる等時間のかかる手続きに進んでいきます。家主側の負担は大変大きいものとなってくるのが実情です。