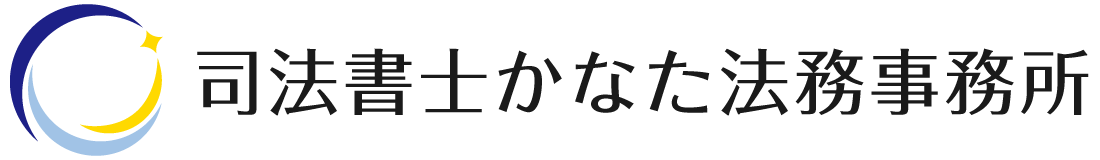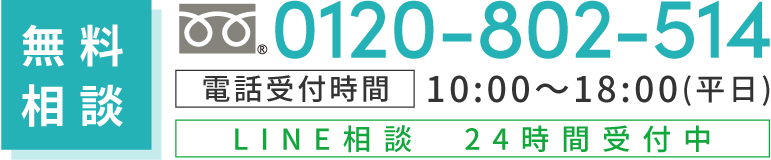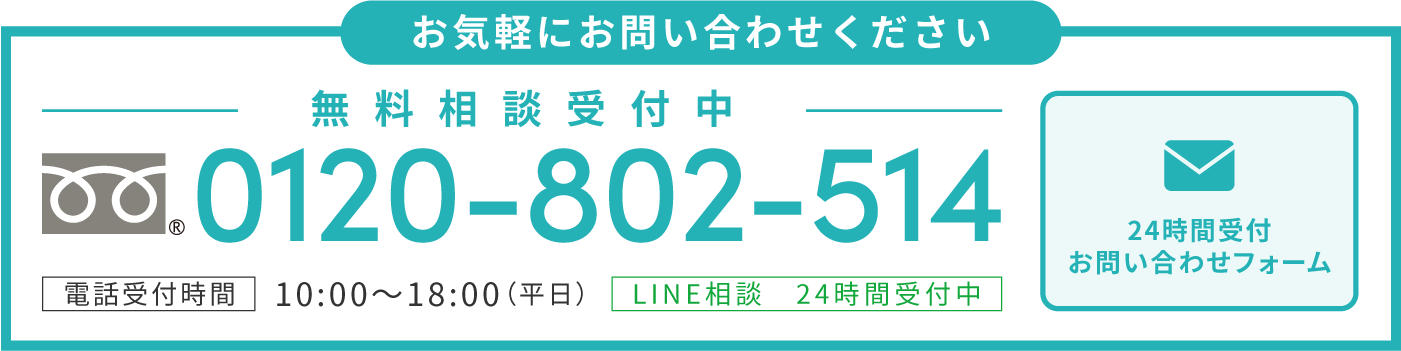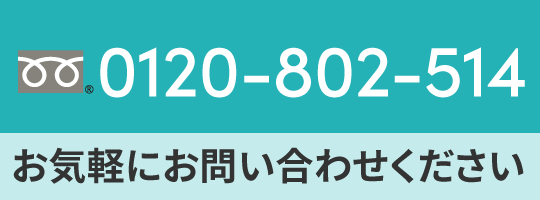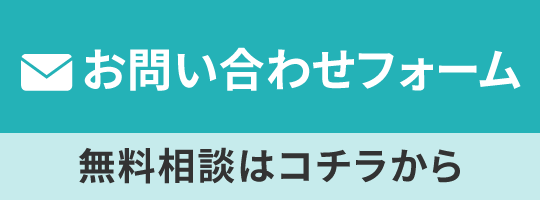このページの目次
1. 終活ブームと遺言書の増加
遺言書は「遺書」と言葉が似ていることから、縁起が悪いとタブー視されていましたが、最近の就活ブームにおって、自分の思いを実現させたいという方が増え、遺言書を作成する人も増えてきています。
実際に、インターネットで検索すると、遺言書の書き方を説明するホームページもたくさん見られます。それだけ、遺言書作成が身近になりつつあることかもしれません。
しかし、遺言書の書き方を指南しているホームページの中には、法的に遺言書として認められないものも見受けられます。
実は、遺言書の書き方については民法に厳格なルールが決められています。
このルールを知らずに遺言書を作ってしまったことにより、その遺言書が無効となり、かえって相続人間の争いが発生するケースもあります。
このようなトラブルを避けるために、遺言・相続の専門家である司法書士にまずは相談することをおすすめします。
当事務所では、遺言書作成に必要な書類の収集から、遺言書文案の作成、公証役場の立ち会いまで、トータルで遺言書の作成をサポートします。
2. 遺言書を作成した方が良いケース
特に以下のケースに当てはまる方は遺言書を検討する必要性が高い方です。
- 子供がいない夫婦のケース
- 自分が亡くなった後、残された配偶者の生活が心配なケース
- 相続人の中に行方明者や音信不通の方がいるケース
- 内縁の妻(又は夫)や子供の配偶者など、相続人以外の者に自分の財産を残してあげたい場合
- 再婚し、先妻との間に子供がいるケース
- 相続人同士の仲が悪く、財産を分ける際に相続人間でもめる可能性があるケース
- 事業主であり、事業を継ぐ子に事業用財産を相続させたいケース
3. 遺言書の種類と司法書士に依頼するメリット
遺言書といっても様々な種類の遺言書があることをご存じでしょうか?
実は、民法上は7種類もの遺言が記載されています。
ここでは、代表的な2つの遺言、①自筆証書遺言と②公正証書遺言、そして、自筆証書遺言に代わる③新たな制度(法改正)について説明したいと思います。
① 自筆証書遺言のメリット・デメリット
遺言者本人が、本文・日付・氏名等を自書し、押印して作成する遺言です。
自書するという条件はありますが、筆記具と紙があれば作成することができますので、費用もかからず簡単に作成することができます。
しかし、遺言書の書き方については法律で厳格なルールが定められてあり、このルールに反した遺言書を作ってしまったことにより、その遺言書が無効になってしまう危険性があります。
また、紛失の危険性や自己の死後どのような形で遺言書の存在を相続人に知らせるかといった問題もあります。
さらに、遺言者本人の死後、家庭裁判所の検認が必要となりますので、残された相続人にとっては手間と負担が生じます。
なお、この自筆証書遺言については、2020年7月10日より「自筆証書遺言書保管制度」が導入されました。
② 公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は公証人が作成に関与する遺言です。自筆証書遺言と違って、公証人に支払う費用がかかることと、証人2人の立合いが必要になることから証人を探す必要があります。
しかし、自筆証書遺言と違って記載の不備により無効になる恐れはなく、公証役場で遺言書を保管するので紛失の恐れもありません。
そこで、当事務所でも公正証書遺言の作成をおすすめしています。
誤って作成された遺言書は、遺言自体が無効でありますし、仮に遺言書自体は有効であったとしても遺言書の内容によって、かえって相続人間のトラブルの原因になることがあります。
司法書士は法律の専門家ですので、司法書士が遺言書の作成に関与することにより、このような問題点に適切に対処することができます。
また、遺言で司法書士を「遺言執行者」として指定しておけば、実際に相続が発生したときに預貯金の解約や相続登記といった手続きを円滑に進めることができます。
③ 自筆証書遺言に代わる新たな制度(遺言書保管制度)
遺言書作成の高まりを受けて、自筆証書遺言にあるデメリットを解消する制度として、2020年7月10日から、法務局での遺言書の保管制度がスタートしました。
これは、自筆証書遺言を法務局に提出し、保管してもらうことにより、事前に形式的なチェックを法務局から受けられるメリット、そして、紛失や改ざんの恐れがなくなるというメリットがあります。
また、遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言については、家庭裁判所の兼任手続きが不要とされました。
これは、残された相続人にとってはかなりの負担軽減となります。
しかし、デメリットもあります。
遺言書保管制度の唯一のデメリットは、申請手続きは必ず本人自らが法務局の窓口に出向いてする必要があるという点です。
司法書士、弁護士、ご家族が代理で申請することは認められていません。この点が唯一の難点といえると思います。
まとめ
| メリット | デメリット | |
| 自筆証書遺言 | ・安価で簡単に作成できる ・いつでも書き直しが可能 |
・紛失や他人の改ざんの恐れ ・死後に家裁の検認手続きが必要 |
| 公正証書遺言 | ・中身についても公証人のチェックが受けられる ・紛失や改ざんの恐れがない ・遺言の確実性を担保できる ・死後の家裁の検認手続きは不要 |
・自筆証書遺言より費用がかかる |
| 遺言書保管制度 ※2022年~の新制度 |
・法務局による事前のチェックが受けられる(形式のみ) ・紛失や改ざんの恐れがない |
・本人が窓口に出向く必要あり(代理では行えない) |
4. 様々な相続手続き
相続が発生した場合、実に多くの様々な手続をしなければいけません。
手続きの中には期限が定められているものあり、迅速に手続を行う必要があります。
| 死亡届の提出 | 7日以内 |
| 相続放棄等の手続き | 3ヶ月以内 |
| 被相続人の準確定申告 | 4ヶ月以内 |
| 相続財産(不動産・株式・預貯金等)の名義変更 | 不動産につき、3年以内 |
| 相続税の申告と納付 | 10ヶ月以内 |
| 生命保険金の請求 | 3年以内 |
これらの手続をご自身でするのはとても労力がかかります。
また、どの専門家に頼めばいいのか戸惑うことも多いと思います。
不動産の名義変更や相続放棄等は司法書士、相続税の申告は税理士、遺産分割協議がこじれた場合は弁護士、年金に関する手続は社会保険労務士等、様々な専門家が関与します。
このように専門家を自分で一人一人探していくのは負担もあり面倒なことです。
そこで、当事務所では他の士業と協力し幅広い相続手続をトータルサポートすることにより円満な相続手続きを実現できる体制を取っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
5. 相続手続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した場合、戸籍を集め相続人を確定させます。
そして、被相続人が残した財産を把握した上で、遺産分割協議を行います。
また、相続財産(不動産・株式・預貯金等)の名義変更に使う遺産分割協議書には手続きをスムーズに進ませるための書き方のコツがあります。
ご自身で相続手続きをすることはもちろん可能です。
しかし、「遺産分割協議書に不備があり、法務局からこの遺産分割協議書は不動産名義変更に使えないと言われてしまった」というご相談を当事務所で受けることも少なくありません。
当事務所では戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、名義変更まで幅広くサポートいたします。
ご相談・お見積は無料ですので、お気軽にご相談ください。