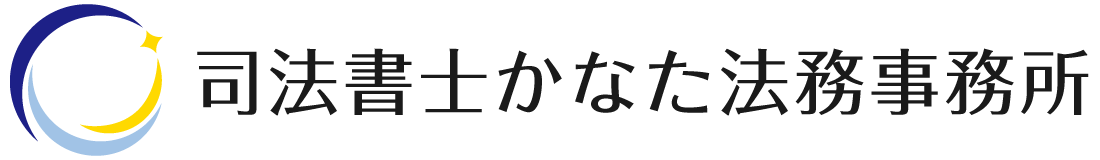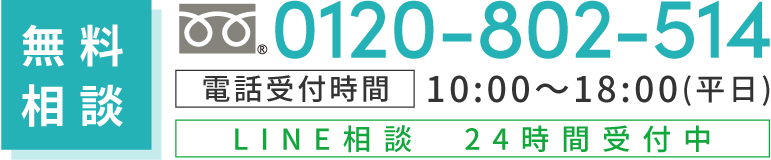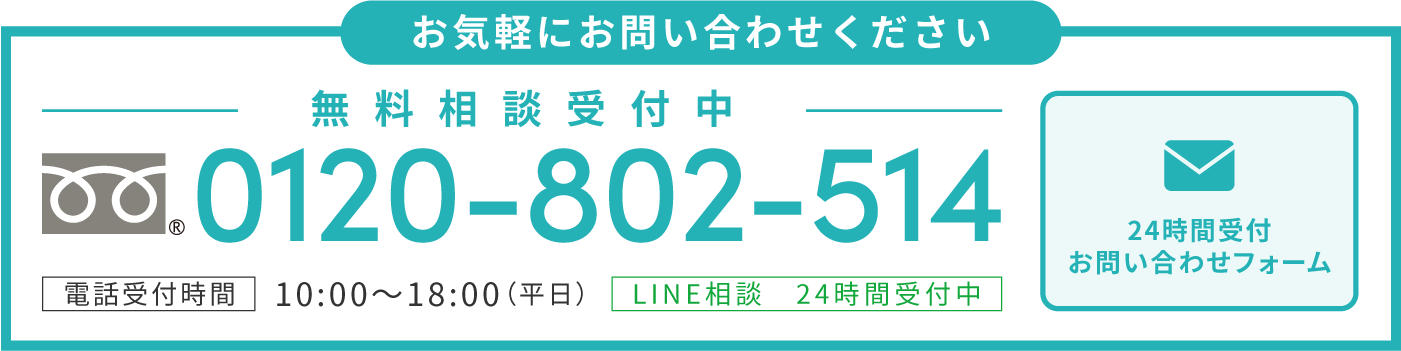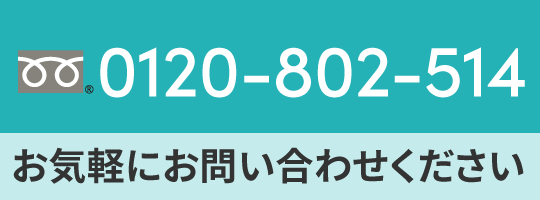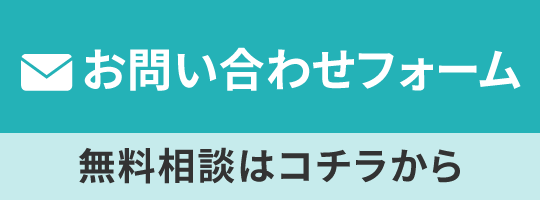家族や親族が亡くなった際、相続人はプラスの財産だけでなく、借金などの負債も相続する可能性があります。
そのため、借金を引き継ぎたくない場合には、相続放棄を選択することができます。
しかし、相続放棄には期限があり、「相続開始を知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)」に家庭裁判所への申立書を提出する手続きをしなければなりません。3ヶ月以内に、相続放棄の手続をせず期間が過ぎた場合には、相続を単純承認したものとみなされ、被相続人の遺産を借金とともに全て引く継ぐことになってしまいます。
しかし、3ヶ月が過ぎてしばらくしてから被相続人に多額の借金があることが判明したということもよくあることです。
この場合でも3ヶ月が過ぎた以上、相続放棄をすることができないのが原則です。
では、熟慮期間を超過してしまった場合に相続放棄は一切認められないのでしょうか?
実は、一定の特別事情がある場合には、3か月の期限後申立が認められる可能性があります。本記事では、3ヶ月の期間を超えてしまった場合の相続放棄の可否や、申立ての手続き方法について詳しく解説します。
このページの目次
1. 相続放棄の熟慮期間とは?
熟慮期間の基本ルール
民法では、相続放棄は「相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立てを行う必要があると定められています(民法915条)。
この期間内に手続きを行わなかった場合、原則として「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。
つまり、被相続人の借金もすべて引き継ぐことになってしまいます。
2. 熟慮期間を超えた相続放棄が認められるケース
昭和59年の最高裁判所の判決
実は判例で、3ヶ月を過ぎてしまった場合にも、「特別な事情」ある場合には、3ヶ月が経過した後でも、例外的に、相続放棄の申立てをすることができる場合があるとされています。
「特別な事情」とは?
では、判例で述べられている特別の事情とはどのようなものでしょうか。以下解説します。
① 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること
例:被相続人と疎遠であったため、故人の財産状況を知ることが出来ずに、また、故人を知る人から「財産は何もない」ということを聞かされていたため、特に相続放棄の手続きを取らずに放置した。
② 相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
例:被相続人と関係性が悪く、疎遠であったため財産調査などができなかった。
上記のような「特別な事情」がある場合には、熟慮期間の起算点、スタート地点を、「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時」から計算するとされました。
難しい言い回しとなっていますが、結論としては、「負債の存在を知った時」から3ヶ月以内に相続放棄をすればよいということになります。
3. 熟慮期間超過後の相続放棄の手続き方法
熟慮期間を超えてしまった場合でも、相続放棄を申立てるには、家庭裁判所へ申立て手続きを行う必要があります。
申立ての流れ
① 相続放棄申述書を作成
家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」を作成します。
記載内容:
- 申立人(相続人)の氏名・住所
- 被相続人の氏名・死亡日
- 相続を知った日
- 熟慮期間を過ぎた理由(特別事情)
- 延長を求める正当な理由

② 必要書類を準備
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の指定様式)
- 被相続人の戸籍謄本
- 申立人(相続人)の戸籍謄本
- 特別事情を証明する資料(借金発覚の証拠など)

③ 家庭裁判所へ申立てを行う
相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出します。

④ 裁判所の審査を待つ
提出後、家庭裁判所が特別事情が認められるか審査します。通常、1〜2ヶ月程度で判断が下されます。
- 認められた場合: 相続放棄が成立し、借金の返済義務がなくなる
- 却下された場合: 相続放棄が認められず、借金を引き継ぐことになる
4. 3ヶ月経過後の相続放棄が認められるためのポイント
あくまで、期間経過後の相続放棄の申立ては、例外的な取扱いになります。
そのため、「特別の事情」があるということを、客観的な資料を基に、丁寧に裁判所に説明する技術が求められます。
実務上は、「上申書」を作成して、今回のケースが「特別の事情」の条件を満たしていることを証明していきます。
申立てが認められる保証はない!?
家庭裁判所の判断次第で、相続放棄が認められないこともあります。確実に手続きを進めるためには、証拠をしっかり準備することが重要です。
事務所によって結果が変わってしまう!?
実は、この3ヶ月経過後の相続放棄の申立ては、事務所の力量の差が出てしまうところになります。正直なところ、経験がない事務所では、どのような書類を作成すれば裁判所に認められるかが分からないと思います。
このような文書を書けば認められるといった書式や書籍もありません。そのため、どうしても事務所によって経験の差がでてきてしまうところになります。
当事務所では、3ヶ月経過後の申立を行った実績も豊富にあるため安心していただけると思います。
5. まとめ|熟慮期間超過後でも諦めずに対応を
相続放棄には原則3ヶ月の熟慮期間がありますが、例外的に期限後申立が認められる場合があります。
- 3ヶ月経過後に借金の存在を知らなかった場合や、特別事情がある場合は、家庭裁判所に申立て可能
- 期限後の相続放棄を希望する場合は、証拠を準備し、早めに手続きを行うことが重要
- 認められるかどうかは家庭裁判所の判断次第なので、経験のある専門家に相談するのがおすすめ
もし熟慮期間を超えてしまった場合でも、特別な事情があれば諦めずに相続放棄を検討することは重要です。
当事務所では相続放棄が認められるように事情を詳しく聞きながらあらゆる観点から必要な書面を作成し、家庭裁判所に説明をしていきます。